事業承継とは?種類・進め方・M&Aによる第三者承継までわかりやすく解説
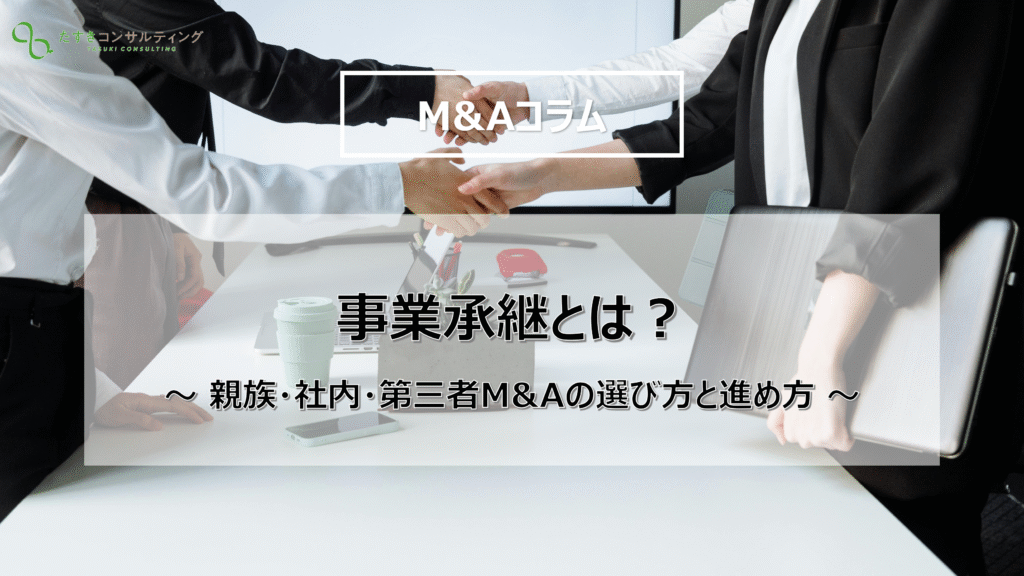
【2025年11月更新】
事業承継とは、会社の経営や資産を次世代へ引き継ぐことを指します。経営者の高齢化が進む中、多くの中小企業が「後継者不在」という課題を抱えています。
本記事では、事業承継の種類・手順・準備方法をわかりやすく整理し、近年注目されるM&Aによる第三者承継の仕組みやメリットも詳しく解説します。中小企業経営者の方が、最適な承継方法を選ぶための実践ガイドです。
目次
事業承継とは?
事業承継とは、企業の経営権や資産、人材、ノウハウなどを次世代に引き継ぐプロセスです。一般的には、経営者の引退や死亡をきっかけに行われますが、計画的な準備が重要とされています。中小企業庁のデータによれば、70歳以上になる中小企業経営者約245万人のうち、約半数の127万人が後継者未定と見込まれており、事業承継は日本経済にとっても喫緊の課題です。
【出典:「中小 M&A ガイドライン(第3版)」中小企業庁】
事業承継の3つの方法|親族内・従業員・第三者(M&A)承継
親族内承継
家族、特に子どもに会社を引き継ぐ方法です。企業文化や信頼関係を維持しやすい反面、適任者がいないケースも多く見られます。
従業員承継(社内承継)
役員や幹部など社内の従業員に承継する方法です。企業理解が深い反面、資金調達や経営責任の負担が大きくなることがあります。
第三者承継(M&A)
外部の企業や投資家に会社を売却し、承継する方法です。近年増加しており、後継者がいない企業にとって有力な選択肢です。
| 承継方法 | 概要 | メリット | デメリット |
| 親族内承継 | 経営者の家族(主に子ども)へ引き継ぐ | 社内外の信頼が維持しやすい | 適任者がいない場合もある |
| 従業員承継(社内承継) | 社内の役員や幹部が後継者となる | 企業文化やノウハウが継承されやすい | 経営能力や資金調達に不安が残る場合も |
| 第三者承継(M&A) | 外部の企業・投資家へ事業を譲渡 | 高値売却や成長戦略が期待できる | 社内の理解や買い手選定が必要 |
事業承継の進め方・手順|5つのステップでわかる実践プロセス
1.現状分析・課題把握
- 自社の経営状況や財務内容、組織体制、後継者候補の有無を確認します。
- 業界の動向や自社の強み・弱みを洗い出し、承継に向けたリスクを把握します。
2.承継計画の策定
- 誰に、いつ、どのように承継するかを明確にし、段階的なスケジュールを作成します。
- 承継方法(親族内、従業員、M&A)の選定や、資産・株式の移転方法なども検討します。
3.実行準備
- 承継に必要な手続き(登記、契約、株式移動など)の準備を進めます。
- 従業員・取引先などステークホルダーへの周知や、社内体制の見直しも重要です。
- 税務・法務面の整理も専門家と連携して行います。
4.承継実行
- 実際に株式や事業を移転し、新体制への移行を進めます。
- 必要に応じて経営権の引継ぎ式や対外的な発表なども行います。
5.承継後のフォロー
- 新経営者のサポート体制を整え、一定期間は旧経営者が助言・支援を行うことも有効です。
- 組織の安定化や、企業文化の継承に向けた社内コミュニケーションが欠かせません。
M&Aを活用した事業承継とは?|第三者承継による新たな選択肢
後継者が不在の中小企業にとって、M&Aを活用した第三者承継は、現実的かつ有効な選択肢です。事業承継型M&Aとは、経営者が引退や世代交代を機に、自社を外部の企業や投資家に譲渡し、企業を存続・発展させる手法です。
M&Aによる事業承継を検討する際は、「M&Aの流れ」や「仲介会社の選び方」を理解しておくことが重要です。
M&Aによる事業承継の主なメリット
- 高値売却の可能性:企業の将来性やシナジーを評価されることで、想定以上の価格で譲渡できる場合もあります。
- 従業員の雇用維持:買い手が既存の体制や人材を評価すれば、雇用や取引関係が守られる可能性が高くなります。
- 経営資源の強化:新たなグループの一員になることで、販路拡大や設備投資、経営ノウハウの取得などが期待できます。
M&Aを選ぶ際のポイント
- 相手企業の選定:単なる金額だけでなく、企業文化や将来ビジョンの合致が重要です。
- 適正な企業評価:自社の価値を客観的に算出することで、納得感のある条件交渉が可能になります。
- 信頼できるアドバイザーの活用:初めてのM&Aでは、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。
事業承継型M&Aは「会社を売る」のではなく、「会社を未来につなぐ」ための手段として捉えることで、経営者・従業員・取引先の三方にとって納得のいく選択肢となり得ます。
事業承継でよくある課題と対策
事業承継の過程では、多くの経営者が以下のような課題に直面します。それぞれの課題について、事前に準備や対応策を講じておくことが重要です。
後継者が見つからない
経営者の子どもが継ぐ意思を示さない、適任者が社内にいないなど、後継者の不在は最も多い課題の一つです。このような場合、M&Aによる第三者承継という選択肢を視野に入れることで、企業の存続を図ることができます。
親族・従業員との感情的な対立
誰に継がせるかという問題は、親族間や従業員との間で感情的な摩擦を生むことがあります。早期に方針を示し、丁寧に説明を重ねることで、信頼関係を保ちつつ承継を進めることが可能になります。
準備不足によるトラブル
「まだ早い」と準備を後回しにしていると、経営者の急な引退や健康問題により、対応が間に合わないリスクがあります。事業承継は5~10年単位の時間をかけて進めるのが理想です。
税務・法務上の負担
事業承継には、相続税・贈与税、株式評価、契約書の整備など多くの法務・税務手続きが伴います。これらを自己判断で進めるのではなく、税理士や弁護士といった専門家の支援を受けることが重要です。
以上のような課題に対し、たすきコンサルティングでは中立的な立場から助言を行い、円滑な事業承継を実現するための支援体制を整えています。
事業承継に関する支援制度・補助金|事業承継税制・M&A支援機関登録制度も解説
近年では、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」も創設されており、信頼できる仲介会社・専門家を選ぶ指標として注目されています。事業承継をスムーズに進めるためには、国や自治体が用意している各種支援制度や補助金を上手に活用することが重要です。以下に代表的な制度をご紹介します。
事業承継・引継ぎ補助金(中小企業庁)
中小企業が事業承継・M&Aを実施する際にかかる費用(専門家への相談料、設備投資費用、販路開拓費など)に対して補助が受けられる制度です。毎年募集時期が決まっており、要件を満たすことで数百万円単位の補助が可能です。
【出典:事業承継・M&A補助金│中小企業庁】
事業承継税制
一定の要件を満たすことで、自社株の贈与や相続に伴う相続税・贈与税の納税が猶予され、実質的な税負担を軽減することができます。親族内承継や社内承継を選択する際に有効な制度です。
支援機関による無料相談・サポート
各都道府県には「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されており、承継計画の策定支援やM&Aの初期相談などを無料で受けることができます。商工会議所やよろず支援拠点などでも相談可能です。
これらの制度を上手に活用することで、事業承継に伴う経済的・心理的な負担を軽減し、スムーズなバトンタッチが実現できます。
M&A仲介会社を活用するメリット
M&Aによる事業承継を検討する際、自社だけで進めようとすると相手探しや条件交渉、法務・税務手続きなど、非常に多くの課題に直面します。そこで役立つのが、M&A仲介会社のサポートです。以下のようなメリットがあります。
適切な買い手とのマッチング
業種やエリア、企業規模などの希望条件に応じて、信頼できる買い手候補をリストアップし、成約可能性の高いマッチングを実現します。
専門的な企業評価と価格交渉
自社の適正な価値を客観的に算定し、買い手との価格交渉において有利に進めるための戦略を提供します。
契約・手続きの全面支援
秘密保持契約(NDA)から基本合意、最終契約に至るまでの各種書類作成や調整を一貫してサポートします。
PMI(統合後の支援)まで対応
譲渡後の組織統合や人材マネジメント、社内外への周知など、成約後のフォロー体制も整っています。
たすきコンサルティングでは、M&Aを通じた事業承継において、経営者の想いと企業の価値を大切にしながら、最適な譲渡先の選定から成約後の支援までワンストップで対応しています。
まとめ|事業承継を成功に導くカギは「早期準備」と「専門家との連携」
事業承継は、企業の将来を左右する重要な経営テーマです。
親族に引き継ぐ「親族内承継」、従業員に任せる「社内承継」、そして外部の企業や投資家に託す「第三者承継(M&A)」。
それぞれに異なるメリット・デメリットがあり、自社の現状に応じた最適な方法を見極めることが欠かせません。
成功のポイントは、「早めの準備」と「信頼できる専門家との連携」です。
事業承継は、税務・法務・評価・交渉など多面的な判断が求められるため、専門知識を持つM&A支援機関と協力して進めることで、リスクを抑えながらスムーズな承継が実現します。
たすきコンサルティングは、中小企業庁が定める「M&A支援機関登録制度」に登録しており、さらにM&A支援機関協会にも加盟しています。
厳しい基準を満たした信頼性の高い支援機関として、経営者の想いを大切に、親族・従業員・第三者承継すべての選択肢に対応しています。
たすきコンサルティングは、その想いに寄り添いながら最適な承継プランをご提案します。後継者問題や承継の進め方にお悩みの方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。 是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。
株式会社たすきコンサルティング
お電話でのお問合せ ➿0120-007-888


