【2025年最新版】調剤薬局M&Aの最新動向|事業承継の課題と成功の秘訣
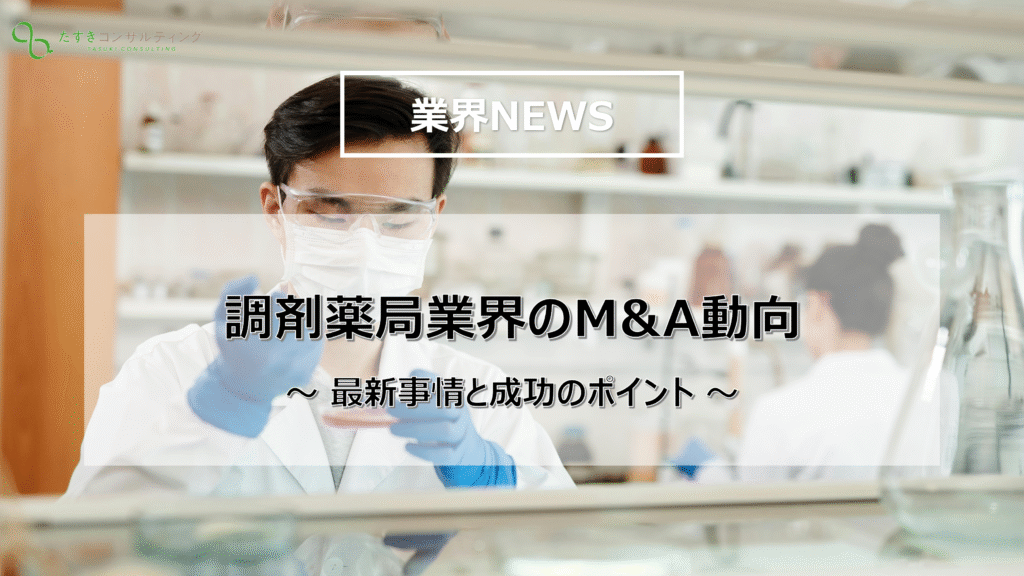
日本の調剤薬局業界は、高齢化の進展や地域医療構想の推進、薬剤師不足など、さまざまな課題に直面しています。これらの要因により、事業承継やM&Aを検討する薬局経営者が増加しています。本記事では、調剤薬局業界の最新動向やM&Aの現状、成功事例、メリット・リスク、そして今後の展望について詳しく解説します。
【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】
中小企業の事業承継を支援するM&A仲介会社であり、約20年の財務コンサルティング実績を有する。公認会計士や税理士などの専門家が在籍し、全国規模で中小企業のM&Aをサポートしております。
※中小企業庁「M&A支援機関登録制度」登録済み
※一般社団法人「M&A支援機関協会」登録済み
※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
目次
調剤薬局業界とは?
調剤薬局とは、医師の処方箋に基づき、薬剤師が医薬品を調剤・提供する薬局を指します。多くの調剤薬局は「保険薬局」として、健康保険制度に基づいた調剤を行っています。これらの薬局は、地域医療の一翼を担い、患者の健康管理や服薬指導など、医療サービスの提供に重要な役割を果たしています。
業界概況|調剤薬局業界を取り巻く環境変化
2025年現在、調剤薬局業界は以下のような環境変化に直面しています。
高齢化の進展:医療・調剤ニーズの増大と薬局の社会的役割の変化
内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、2023年10月1日現在、日本の総人口は1億2,435万人であり、65歳以上の高齢者は3,623万人、全体の29.1%を占めています。また、将来推計では、2070年には高齢化率が38.7%に達し、国民の約2.6人に1人が65歳以上となると見込まれています。
高齢者は慢性疾患の治療のために複数の薬を常用する傾向があり、薬剤師による服薬管理、副作用防止、重複投薬のチェックといった「対人業務」の重要性が高まっています。このような背景から、薬局には、単なる「薬を渡す場所」から、「患者の生活に寄り添う医療拠点」への転換が求められています。
【出典元:内閣府「令和6年版高齢社会白書(全体版)」第1章 第1節「高齢化の状況」】
医療費抑制政策:薬価・調剤報酬の継続的な引き下げで薬局経営に影響
厚生労働省は毎年のように薬価改定を実施しており、調剤薬局の主な収益源である薬剤料が削減されています。2024年度(令和6年度)の「調剤報酬改定」では、以下のような見直しが実施されました。
- 調剤基本料(特に小規模薬局)の引き下げ
- 後発医薬品体制加算の厳格化
- 地域支援体制加算の要件強化
【出典元:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定」】
このように小規模・個人経営の薬局にとっては、報酬制度の改定がダイレクトに経営を圧迫する要因となっており、M&Aや撤退を検討する動機となっています。
地域医療構想の推進:在宅医療・連携重視による薬局の機能分化
国は、団塊世代がすべて75歳以上になる2025年を見据え、地域包括ケアシステムの構築を進めています。
【出典元:厚生労働省「地域包括ケアシステム」】
また、薬局にも「地域に根差した医療機能の担い手」としての役割が求められ、
- 在宅訪問薬剤管理指導
- 医師・看護師・ケアマネジャーとの情報共有
- 服薬情報提供書(トレーシングレポート)の作成
といった業務が増加しています。このような変化に対応できる体制構築が困難な薬局ほど、より大きな資本力を持つ企業との統合(M&A)を選択する傾向にあります。
デジタル化の進展:電子処方箋やオンライン服薬指導などの制度導入
電子処方箋制度は、2023年1月より全国で本格運用が開始されました。
【出典元:厚生労働省「電子処方箋の現況と今後の対応」】
さらに、2020年の法改正により可能となったオンライン服薬指導が普及しつつあり、薬局もITインフラ(電子薬歴、ビデオ会議システム、デジタル署名など)への対応が求められています。こうした対応にはコストと人材が必要であり、特に小規模薬局では設備投資が困難な場合が多く、経営統合や業務提携を通じたデジタル対応が進んでいます。
調剤薬局業界の課題と事業承継ニーズ
調剤薬局業界が直面する主な課題と、それに伴う事業承継のニーズは以下の通りです。
- 薬剤師不足
- 後継者不在
- 収益性の低下
調剤薬局業界では、経営に大きな影響を与える3つの課題が顕在化しています。まず、薬剤師不足です。特に地方では人材確保が難しく、在宅医療など新たな業務に対応できる人材が不足しています。
次に、後継者不在の問題です。経営者の高齢化が進む一方で、親族に継ぐ人がいないケースが増えており、事業承継が困難になっています。
さらに、収益性の低下も深刻です。薬価改定や調剤報酬の見直しにより、特に小規模薬局では利益が圧縮され、経営の継続が厳しくなっています。
こうした背景から、将来を見据えてM&Aなど第三者への承継を検討する薬局が増えています。
調剤薬局業界におけるM&Aの動向
2025年の調剤薬局業界では、以下のようなM&Aの動向が見られます。
大手チェーンによる買収
近年、調剤薬局業界では大手チェーンによる買収が活発化しています。これは、少子高齢化や医療費抑制政策、薬価制度の改定などにより中小規模の薬局の経営が厳しくなっていることが背景にあります。大手企業は、規模の拡大や経営効率化を目的として、M&Aを通じて店舗数を増やし、競争力を強化しています。
地域密着型のM&A
近年、調剤薬局業界では大手チェーンによる買収が活発化しています。これは、少子高齢化や医療費抑制政策、薬価制度の改定などにより中小規模の薬局の経営が厳しくなっていることが背景にあります。大手企業は、規模の拡大や経営効率化を目的として、M&Aを通じて店舗数を増やし、競争力を強化しています。
業態転換の促進
調剤薬局業界では、在宅医療やオンライン服薬指導など、新たなサービスへの対応が求められています。これに対応するため、業態転換を目的としたM&Aが進行しています。例えば、在宅医療に特化した薬局や、IT技術を活用したサービスを提供する薬局との統合により、業務の多様化と効率化を図る動きが見られます。
成功事例|調剤薬局のM&Aによる事業承継
■ アインホールディングスの地域拡大戦略に基づくM&A(2025年3月)
アインホールディングスは、全国規模での店舗展開を進める中で、地域密着型の調剤薬局チェーンを積極的に買収しています。2025年3月には、新潟県で30店舗を運営するエーアンドエムの全株式を取得し、子会社化を発表しました。この買収により、アインホールディングスの店舗数は1270店舗を超え、地域医療への貢献と企業価値の向上を図っています。
【出典元:株式会社エーアンドエムの株式取得に関するお知らせ】
■ アイセイ薬局グループによるオンライン漢方相談サービス『わたし漢方』の事業譲受(2023年12月)
アイセイ薬局グループは、わたし漢方株式会社が運営するオンライン漢方相談サービス『わたし漢方』の事業を譲受したことを発表しました。この譲受は、アイセイ薬局の100%子会社である株式会社AXISを通じて行われました。
【出典元:株式会社アイセイ薬局│PR TIMES】
■ クオールホールディングスによる調剤薬局グループの取得(2023年5月)
クオールホールディングスは、調剤薬局業界の再編に対応するため、積極的なM&A戦略を展開しています。2023年5月には、第一三共の連結子会社である第一三共エスファ(DSEP)の全株式を取得し、子会社化することを発表しました。この買収により、クオールホールディングスは、ジェネリック医薬品事業の拡充と医療関連事業の強化を図っています。
【出典元:第一三共エスファの株式譲渡(連結子会社の異動)に関するお知らせ】
■ ウエルシアホールディングスによるコクミン・フレンチの子会社化(2022年1月)
ウエルシアホールディングス株式会社は、株式会社コクミンおよび株式会社フレンチの株式を取得し、資本業務提携(子会社化)することを発表しました。この取り組みは、都市型店舗の強化と全国への出店網拡大を目的としています。
【出典元:株式会社コクミン及び株式会社フレンチとの資本業務提携(子会社化)に関するお知らせ】
■ マツキヨココカラ&カンパニーによる三重県の調剤薬局3社の子会社化(2021年7月)
マツキヨココカラ&カンパニー(旧ココカラファイン)は、三重県で調剤薬局を展開する以下の3社の全株式を取得し、子会社化したことを発表しました。
- 有限会社イー・ウェル(津市)
- 有限会社ウェル・サポート(津市)
- 有限会社メディカル・サポート(松阪市)
これらの企業は、それぞれ1店舗の調剤薬局を運営しており、地域に根ざした医療サービスを提供しています。本件の株式取得により、マツキヨココカラ&カンパニーは三重県におけるドミナント戦略を強化し、地域のヘルスケアネットワークの構築を推進しています。
【出典元:有限会社イー・ウェル、有限会社ウェル・サポート、 有限会社メディカル・サポートの株式取得に関するお知らせ】
調剤薬局業界におけるM&Aのメリット
M&Aのメリット
- 従業員の雇用維持
- 人材確保の容易化
- 経営資源の共有
調剤薬局がM&Aを活用することで、経営上のさまざまなメリットが得られます。
まず、従業員の雇用が維持しやすくなる点が挙げられます。M&Aによって事業が継続されるため、店舗の閉鎖や退職といった事態を回避し、既存のスタッフの働く場を確保できます。
また、人材確保も容易になります。特に人手不足が深刻な地方では、M&Aによって大手企業の採用力や教育体制を活用でき、薬剤師や事務スタッフの安定的な確保につながります。
さらに、経営資源の共有も大きなメリットです。仕入れコストの削減、ITシステムの導入、店舗運営ノウハウの共有などにより、単独では難しかった経営効率化が実現できます。
M&Aに伴うリスクと対策
- 地域医療への影響
- 従業員の離職リスク
一方で、M&Aには一定のリスクも伴います。
ひとつは、地域医療への影響です。買収後に店舗のサービス方針が大きく変わると、患者からの信頼が損なわれたり、かかりつけ薬局としての役割が弱まる可能性があります。対策としては、M&A後も地域に寄り添った経営方針を維持することが重要です。
もうひとつは、従業員の離職リスクです。経営者の交代や就業環境の変化によって、従業員が不安を感じ、退職につながるケースもあります。このリスクを抑えるには、M&A前後でしっかりと情報共有を行い、待遇や雇用条件に関する透明性を確保することが必要です。
調剤薬局業界において事業承継を成功させるためのM&Aポイント
調剤薬局の事業承継では、薬剤師資格や調剤報酬制度など、業界特有の条件を踏まえた対応が不可欠です。以下のポイントを押さえることで、円滑かつ実効性のあるM&Aを実現できます。

処方元との関係・立地・地域特性を整理する
調剤薬局のM&Aでは、処方箋の発行元(クリニックや病院)との関係性が極めて重要です。医療機関との信頼関係や距離、患者数の安定性などを事前に把握し、買い手にとってのリスクや継続性の有無を明確化しておく必要があります。
「薬剤師の引継ぎ」対策を講じる
薬剤師は国家資格であり、地域によっては人材確保が非常に困難です。特に1人薬剤師体制の薬局では、承継後の継続が困難になるケースもあるため、
- 譲渡後も一定期間は現経営者が関与する
- 薬剤師の雇用継続に向けた事前交渉を行う
といった人的体制の確保がM&A成功のカギとなります。
加算・施設基準の継続を意識する
調剤報酬の中でも「地域支援体制加算」や「かかりつけ薬剤師指導料」など、施設基準の継続認定が承継後の収益を大きく左右します。買い手にとって魅力的な薬局となるためには、
- 必要な届出が維持されているか
- 薬歴管理、在宅対応、トレーシングレポート提出などが適切に行われているか
をチェックし、報酬体系の安定性を示すことが重要です。
医薬品在庫や契約関係を事前に整理する
調剤薬局では、在庫薬品の評価や買掛・売掛の管理、医薬品卸との契約内容が譲渡交渉に影響を与える場合があります。在庫はM&A評価額に含まれることも多く、適正な棚卸や価格算定を早期に行っておくことがスムーズな引継ぎに繋がります。
薬局M&Aに強い専門家を活用する
調剤薬局のM&Aには、薬機法や診療報酬制度、保険薬局の指定など、一般企業とは異なる制度知識が求められます。医療M&Aの実績があるアドバイザーや、薬局経営に明るい会計士・弁護士を活用することで、
- 正確な企業価値評価
- スキーム設計(株式譲渡or事業譲渡)
- 許認可の引継ぎ手続き
などの対応が円滑に行えます。
今後の展望|法改正・制度変更の影響と調剤薬局業界の未来
医療DX推進体制整備加算の見直しとデジタル対応の強化
2025年4月の調剤報酬改定により、「医療DX推進体制整備加算」の要件が厳格化されました。これにより、電子処方箋の導入やマイナンバーカードの保険証利用率の向上が求められています。具体的には、紙の処方箋を含むすべての調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録することが義務付けられ、マイナ保険証利用率の基準も引き上げられました。
これらの変更に対応するため、薬局はデジタルインフラの整備やスタッフのITリテラシー向上が不可欠となります。特に中小規模の薬局にとっては、これらの対応が経営の大きな課題となる可能性があります。
【出典元:医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し】
薬機法改正による薬局機能と薬剤師業務の見直し
2025年の薬機法改正では、薬局の役割が「対物業務」から「対人業務」へとシフトすることが求められています。これに伴い、調剤業務の一部外部委託が制度化され、薬剤師が患者とのコミュニケーションや服薬指導に注力できる環境が整備されます。また、遠隔での医薬品販売やオンライン服薬指導の拡充も進められており、薬局のデジタル対応が一層重要となっています。
【出典元:厚生労働省「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」】
地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の推進
地域包括ケアシステムの中で、薬局が果たすべき役割が明確化されています。「地域連携薬局」や「専門医療機関連携薬局」としての認定を受けることで、地域医療への貢献が期待されます。これらの認定を取得するためには、在宅医療への対応や他の医療機関との連携体制の構築が必要です。
薬価改定と経営への影響
2025年度の薬価改定では、薬価引き下げの対象品目がカテゴリ別に決定され、薬局経営に大きな影響を与えています。特に後発医薬品の供給体制の強化や新薬創出の促進が図られており、薬局はこれらの動向を踏まえた経営戦略の見直しが求められます。
【出典元:厚生労働省「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」】
人材確保と働き方改革
少子高齢化の進展により、薬剤師の人材確保が困難になっています。特に地方では薬剤師の流出が顕著であり、デジタル技術の導入や働きやすい環境の整備が求められています。クラウドカメラの活用やAIによる業務支援など、テクノロジーを活用した働き方改革が進められています。
まとめ│調剤薬局の事業承継にM&Aを活用するメリットと今後の対策
調剤薬局業界では、薬剤師不足や後継者不在、制度改正による収益構造の変化など、経営者が直面する課題が年々複雑化しています。こうした背景の中、M&Aを活用した事業承継は、薬局を未来につなぐ有効な手段として注目されています。
M&Aを活用することで、従業員の雇用を守り、買収側のノウハウや資源を取り入れて経営基盤を強化できるといった多くのメリットがあります。また、薬局のサービスを地域に継続的に提供し続けられるという点でも、患者や地域社会にとってプラスの影響をもたらします。
一方で、M&Aには地域医療への影響や従業員の不安といったリスクも伴うため、早期からの準備と専門家の支援が重要です。買収先の選定や、法務・税務・薬機法への対応を含め、計画的な進め方が成功の鍵を握ります。
今後、法制度の変化やデジタル化の加速により、調剤薬局を取り巻く環境はますます変化していくと予想されます。時代に合わせた柔軟な対応と、将来を見据えた承継戦略こそが、薬局経営を持続させる大きな一歩となるでしょう。
譲渡(事業承継)に関するお問い合わせ
事業の譲渡や承継についての第一歩は、専門家への相談から始まります。情報収集や自社評価など、ぜひお気軽にお問い合わせください。下記フォームより、必要事項をご記入の上送信いただければ、迅速にご対応させていただきます。


