会社廃業時の従業員への対応とは?給与・退職金・失業保険をわかりやすく解説
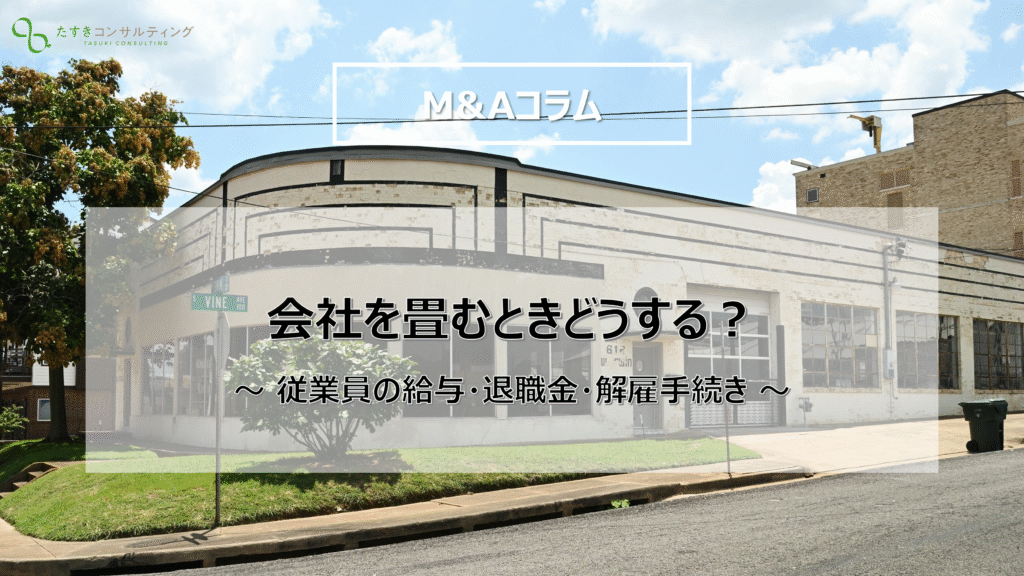
【2025年9月更新】
会社を廃業する際、経営者が避けて通れない重要な課題が「従業員への対応」です。会社廃業時の従業員対応では、給与や退職金の支払い、社会保険や雇用保険の手続き、さらに解雇通知の方法など、多岐にわたる実務が発生します。特に「整理解雇」のルールや解雇予告のタイミングを誤ると、労働トラブルや法的リスクにつながる恐れがあるため、正しい知識を持って準備することが不可欠です。
また、廃業を決断した場合、従業員に対して可能な限り早く通知し、給与・退職金・未消化の有給休暇処理や年末調整などの対応を適切に進める必要があります。さらに、社会保険や雇用保険の資格喪失手続き、従業員が失業保険を受給するための対応も経営者側の重要な責任です。
本記事では、会社廃業に伴う従業員対応の基本知識を網羅し、給与・退職金・解雇手続きから社会保険や雇用保険まで、経営者が押さえておくべき実務上のポイントをわかりやすく解説します。適切な対応を取ることで、従業員への影響を最小限に抑え、円滑に廃業手続きを進めるための参考にしてください。
目次
会社を廃業する場合は、可能な限り早く従業員に通知する
廃業の決定が固まり次第、可能な限り早く従業員に通知することが重要です。直前の通知は従業員に大きな混乱を招くため避けるべきです。公平性を保つため、全従業員が参加できる場で説明し、廃業理由(業績悪化など)を具体的かつ誠実に説明することが大切です。理由だけではなく、従業員が抱える不安を軽減するため、対応策も明確に伝えます。これらは、社長や経営陣が直接説明を行い、誠意を示すことが非常に重要です。
会社を廃業する場合は、従業員を解雇する必要がある
廃業とは、会社や事業主が自発的に事業活動を停止し、会社や事業を閉じることを指します。会社を廃業すると法人が消滅してしまうため、雇用契約は継続できません。したがって、会社を廃業する場合は、従業員を解雇する必要が生じます。
会社を廃業する場合の「整理解雇」とは?
従業員の退職は、「自己都合退職」と「会社都合退職」の2つに分けられます。会社を廃業するために従業員に辞めてもらう場合は、「会社都合退職」となります。
解雇には主に3種類あり、会社を廃業に伴う従業員の解雇は、「整理解雇」に該当します。
| 普通解雇 | 整理解雇 | 懲戒解雇 | |
| 概要 | 従業員の能力不足や勤務態度の問題を理由に行われる一般的な解雇。 | 経営悪化や事業縮小など会社の都合による解雇。 | 従業員の重大な違反行為や不正行為を理由に行われる最も厳しい解雇。 |
| 理由 | ・業務遂行能力の不足 ・勤務態度不良 ・健康上の問題 | ・経営悪化 ・人員削減の必要 ・事業閉鎖、倒産 | ・横領や窃盗 ・業務命令違反 ・ハラスメントや暴力行為 |
さらに、日本の労働法では、整理解雇が正当性を持つために、以下の4つの要件(「整理解雇の4要件」)をすべて満たす必要があります。
【 整理解雇の4要件 】
① 人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
② 解雇回避の努力
配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
③ 人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
④ 解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと
【出典】:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール 3整理解雇」
これらをすべて満たすことで、整理解雇が適法と認められます。不十分な場合、不当解雇とされるリスクが高いため、慎重な計画と対応が求められます。
従業員に解雇を通知するタイミング
会社を廃業する際、従業員への解雇通知は労働基準法第20条に基づき、解雇通知は少なくとも30日前に行う必要があります。適切なタイミングで通知することで、従業員が次の職場を探す準備をする時間を確保し、トラブルを防ぐことができます。
また、解雇通知書は必ず作成して交付することを強く推奨します。解雇通知書は、解雇の理由や条件を明確に示す正式な文書であり、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。
会社を廃業する場合の「従業員の給与」について
会社を廃業する場合、従業員の給与については労働基準法に基づき、未払いの給与や解雇予告手当、有給休暇の未消化分などを適切に精算する必要があります。未払いとなることがないように、退職時にトラブルが起きないようにしましょう。
会社を廃業する場合の従業員の「退職金」について
退職金が規定されている場合
就業規則や労働契約書で退職金に関する条項が明記されている場合、退職金を支払う義務があります。支給基準(勤続年数や給与額に応じた計算方法など)は規定に従います。
退職金が規定されていない場合
法律で退職金の支払いが義務付けられているわけではないため、支払い義務はありません。場合によって、従業員への生活支援や誠意を示すために、退職金に代わる補償金を支払うケースもあります。
会社を廃業する場合の従業員の「有給休暇」について
原則:有給休暇を消化させる
従業員が希望する場合、廃業日や退職日までの期間に有給休暇を消化させることが基本です。退職日までは雇用契約が有効であるため、その期間内に有給休暇を取る権利が保障されます。
有給休暇の買取り
廃業までの期間に有給休暇を消化できない場合、未消化分の有給休暇を金銭で買い上げる対応をすることがあります。法律上、有給休暇の買取りは義務ではありませんが、廃業の場合には誠意を示すために実施する企業が多いです。
有給休暇は、退職日までに消化または買取りするのが原則です。退職後に有給休暇を取得することはできません。
会社を廃業する場合の従業員の「年末調整」について
年末調整は、その年に支払った給与に対する所得税の過不足を精算する目的で行われます。会社を廃業する際、従業員の給与に関する最終的な税務処理として、年末調整を行う必要があるかどうかを確認し、適切に対応することが重要です。
会社がその年の12月31日以前に廃業した場合でも、廃業時点で年末調整を行う義務があります。例外として、従業員が次の就職先で年末調整を行う場合や、本人が確定申告を行う場合、年末調整を省略できます。年末調整を行わない場合でも、源泉徴収票の発行や税務署への報告は忘れずに実施する必要があります。
会社を廃業する場合の従業員の「保険」について
従業員は、勤めている会社を通じて失業保険(雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しています。会社を廃業する場合は、従業員が自ら手続きを行わなければなりません。会社が廃業する際の保険の対応について、ご紹介します。
失業保険(雇用保険)
企業は、離職票(雇用保険被保険者離職証明書)を発行し、従業員が早期に失業手当を受給できるようハローワークを通じて手続きを行います。廃業にともない従業員を整理解雇する場合は、会社都合退職となるため、待機期間なしで早期に受給開始となり、手当の給付日数も通常より多くなります。
社会保険(健康保険・厚生年金)
企業は、廃業に伴い、従業員が健康保険や厚生年金の資格を喪失するため、資格喪失届を年金事務所に提出します。従業員が退職後に健康保険を継続する場合、「任意継続(任意継続被保険者制度)」、「国民健康保険への加入」、「家族の扶養に入る」のいずれかを選べるよう案内する必要があります。また、加入手続きにともない保険や年金の負担が従業員側に生じることになりますので、十分な説明と従業員が安心して手続きできる環境を整備することが重要です。
会社を廃業する場合の従業員の「雇用」について
会社を廃業する場合、従業員の雇用を失わせることになるため、企業側には再就職を支援する社会的責任があります。誠実な対応をすることで従業員の不安を軽減し、廃業に伴うトラブルを防ぐことができます。
【再就職支援の流れ】
| 時期 | 企業の対応 |
|---|---|
| 廃業決定時 | 廃業の理由や予定日を従業員に通知し、再就職支援計画を立案。 |
| 廃業の3ヶ月前 | 求人情報の収集、職業紹介サービスやハローワークとの連携を開始。 |
| 廃業の2ヶ月前 | 再就職支援説明会を実施し、従業員のキャリア相談やスキルアップ研修を提供。 |
| 廃業の1ヶ月前 | 離職票の準備、再就職支援金の支給。 |
| 廃業後 | 離職票交付、従業員がハローワークや求人情報にアクセスできるようサポート。 |
【具体例】
A:同業他社への紹介
廃業後も事業が関連する取引先や同業他社に連絡し、従業員の採用を依頼します。結果として、約半数の従業員が関連会社での再就職を実現するケースもあります。
B:ハローワークとの連携
ハローワークでの再就職支援セミナーに従業員を案内することで、雇用保険の手続きがスムーズに進み、迅速に失業手当を受給することができます。
まとめ│会社を廃業する場合の従業員への対応
会社を廃業する際には、従業員への通知や解雇手続き、給与・退職金・有給休暇の精算、年末調整や社会保険・雇用保険の処理など、多くの実務対応が発生します。対応を誤れば法的リスクや従業員とのトラブルにつながるため、正しい知識をもとに、計画的かつ誠実に進めることが重要です。
一方で、「従業員に不利益を与えたくない」「長年築いた事業を簡単に畳みたくない」と考える経営者も少なくありません。その場合、廃業ではなく M&Aによる事業承継という選択肢があります。M&Aであれば、従業員の雇用を守りつつ事業を次世代へ引き継ぐことが可能であり、取引先や顧客との関係も継続しやすくなります。
廃業を検討している経営者の方も、まずは「廃業」と「M&A」の両面から可能性を比較し、最適な選択肢を見極めることが大切です。
当社は中小企業の事業承継・M&Aに特化した専門家チームが在籍し、財務・税務の観点からもトータルでサポートしています。廃業を検討している方も、まずはお気軽にご相談ください。
当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。
是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。
株式会社たすきコンサルティング
お電話でのお問合せ ➿0120-007-888


